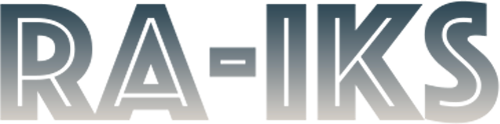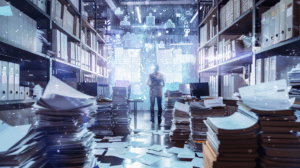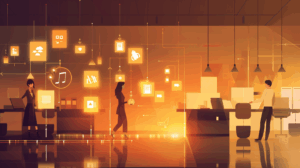生成AIは“仕事ができない天才社員”?──現場で活かすために必要な視点と設計
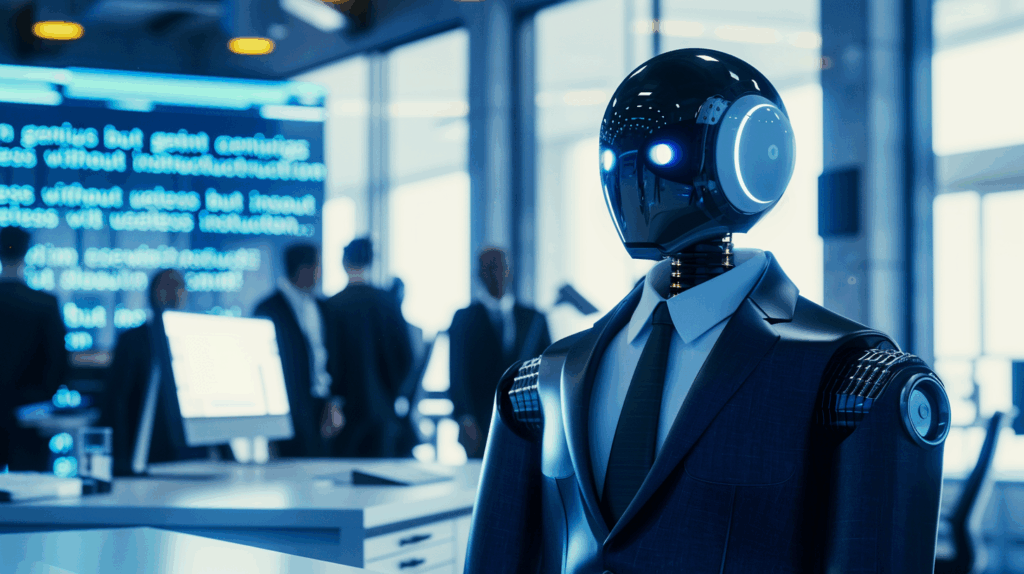
「すごいって聞いたのに、なんでうまくいかないの?」
その違和感、AIが“使えない”のではなく、“使い方”がズレているだけかもしれません。
その違和感、「あなただけ」じゃありません
最近、ChatGPTや生成AIを導入してみたものの、
「正直、思ったほど役に立っていない」と感じていませんか?
- 「文章は書けるけど、内容がずれてる」
- 「指示したことと微妙に違うアウトプットが返ってくる」
- 「手間が減るどころか、チェック作業が増えた」
実は、多くの企業が同じ“つまずき”を経験しています。
「完璧な部下」という誤解
生成AIの導入時、こんなイメージを持たれた方は多いのではないでしょうか。
「知識が豊富、文章も計算もできる。しかも24時間フルタイム労働──まさに理想のパートナー!」
たしかに、生成AIは「言葉を組み立てる力」「膨大な情報をもとに回答する力」に優れています。
しかし――
彼らは“状況を読む”ことができません。
つまり「空気が読めない」のです。
指示が抽象的だったり、前提を伝えていなかったりすると、
いくら頭が良くても「ズレた答え」を出してしまう。
それはまるで、
「学歴は高いけれど、現場の空気を理解せずに浮いてしまう新人社員」そのものです。
生成AIは“指示待ち社員”である
生成AIは、決して万能ではありません。
- 自ら気を利かせて動くことはできない
- 前提条件や背景を汲み取れない
- 文脈がないと、表面的な答えを返す
つまり、まさにテンプレートな指示待ち社員なのです。
逆に言えば、正しく指示すれば、非常に優秀なアウトプットを返してくれる存在とも言えます。
生成AIに対して「イマイチ使えない」と感じている企業は、
AIの能力ではなく、「人間側の設計力」に課題があるケースが多いのです。
カギは“人間側の設計力”にある
では、どうすればこの「天才だけど不器用な社員」を戦力化できるのでしょうか?
答えはシンプルです。
AIを活かす“仕組み”を、人間が用意すること。
具体的には以下のような視点が重要です
- 業務の目的を明確にする:「何のために使うのか」を定義する
- プロンプト(指示文)を設計する:「誰向けに」「どのトーンで」「どんな出力を」まで具体化
- チェック&修正の流れを組み込む:人間による評価・編集を前提にした体制を組む
- “使う人”を育てる:AIの活かし方を現場に浸透させる
AIを使いこなすのではなく、“AIを使いやすくする”設計を行うことこそが成功のカギと言えます。
活用に成功した事例
あたとえば、業務マニュアルの初稿作成に生成AIを活用するケースを想定しましょう。
経済産業省が提供する「生成AIの活用事例」で紹介されているように、生成AIは“たたき”を短時間で作成できる特長があり、AIが出した下書きを人間が補足・修正することが一般的に効率的です。
参考1 経済産業省 「コンテンツ制作のための生成AI利活用ガイドブック」を公表しました(2024年7月5日)https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/aiguidebook.html
参考2 経済産業省 デジタル時代の人材政策に関する検討会
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/index.html
実際の設計例としては、下記のようなことが考えられます。
• 社内用語や製品の特徴など、業務に必要な前提情報を事前に共有
• 過去の優良マニュアルをテンプレートとして学習させ、出力のスタイルを統一
• AIが作成した初稿を、ベテラン社員がレビューするチェック体制を整備
こうした運用を通じて、初稿作成の時間が大幅に短縮されると期待できます。
経済産業省資料でも、「タスクのたたきを短時間で生成し、一部を修正することで時間短縮につながる」と明記されています。
現場からは、「AIが“下書き係”になってくれたおかげで、本来の業務に集中できるようになった」という実感の声も聞かれています。
AIを「任せる」のではなく「活かす」存在に
生成AIは、たしかに賢い。
でも、ただ“使えば成果が出る”ような魔法のツールではありません。
その力を発揮させるためには、人間側の考える力・設計力・共創の視点が必要です。
AIを“仕事ができない天才社員”と捉えることで、
「付き合い方」や「教え方」が変わってくるはずです。
あなたは“AI部下”、ちゃんと育てられていますか?
生成AIは、使い方しだいで頼れるパートナーになります。
その第一歩は、「何が得意で、何が苦手か」を知ることから。