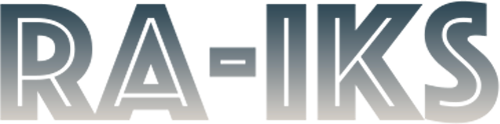グループウェア導入が怖いのは当たり前──だからこそ
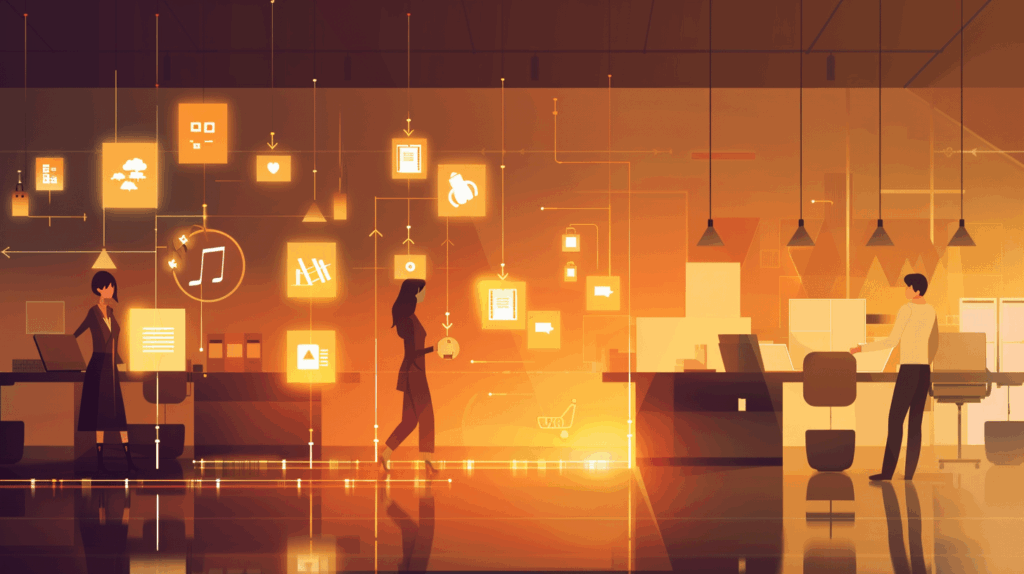
新しいものへの恐怖は当たり前
デジタルツールでもルールでも、新しいものを導入するとき、多くの人が感じるのは「ちゃんと使いこなせるだろうか?」「ちゃんとできるのだろうか?」という不安でしょう。
特にグループウェアのように「社内全員が関わる仕組み」のように多くの人が関わるものは、不安がさらに大きくなります。
「うちの社員に使いこなせるかな」
「むしろ混乱が増えるのではないか」
「前のやり方で十分なのに、わざわざ変える必要ある?」
こなん声が出るのは至極当然です。人は本能的に変化に抵抗します。新しいものにチャレンジするのが“怖い”のは、むしろ健全な反応と言えます。
誰だって最初は初心者だよ
グループウェアを導入したからといって、最初からスムーズに使える人はいません。
当たり前ですが、経営者も、システム担当者も、現場社員も、全員が「初めて触る初心者」からスタートします。
大切なのは「最初はできなくて当たり前」と割り切ることです。
使いながら徐々に慣れていく過程そのものが“学びの時間”なんです。
失敗や戸惑いは「ダメなこと」ではありません。
「慣れるための必要なステップ」です。
使い慣れている人ほど、上手く使える人ほど、見えない場所で多くの失敗をしています。
でも、本人はそれを「失敗」と捉えていなかったりします。
なんでも少しずつなんだ
怖さを小さくするには、「一気に変えないこと」がポイントです。
たとえば、次のようなステップを踏むとスムーズです
まずはスケジュール共有だけ
チャットで雑談してみる?
文書やファイル共有をチャットツールで投稿してみる
こうした「小さく始めたこと」が、導入の怖さを和らげ、積極的な関与に繋がります。
心理学が教えてくれる「少数から多数」の流れ
「怖いから様子を見たい」という心理は、多くの人に共通した考えです。
心理学や社会学では「イノベーター理論(普及学)」といいます。
新しいアイデアや技術は社会に広がるまでに5つ過程があります
• イノベーター(革新者:全体の2.5%)
誰よりも早く、新しいツールに挑戦する人たち。新しい物好きのひとたち
• アーリーアダプター(初期採用者:13.5%)
新しい仕組みを理解し、周囲に広めるリーダー的存在。え?これ便利じゃん!といち早く勘づいて、有効活用する人たち
• アーリーマジョリティ(前期追随者:34%)
「もう大丈夫そうだ」と安心してから導入する層。とにかく失敗したくない!という人たち
• レイトマジョリティ(後期追随者:34%)
多数派が導入してから、ようやく重い腰を上げる層。世の流れに従いまっせ!という人たち
• ラガード(遅滞者:16%)
最後まで導入を避ける人たち。いやいや、得意な人がやれば良いでしょ?という人たち
どんな職場でも、この割合です。
「最初から乗ってくる」のは新しいもの好きの人間(イノベータ)以外いません。
100人いたら2、3人だけです。
その少数の“挑戦者”がどれだけ奮闘するか、どんな成果が出るかで、
大多数が「安心して追従」できるか否かが決まるのです
グループウェアで日常は変わる
最初は覚えることが多くて大変ですが、実際に使い始めると、少しずつ業務のあり方が変わります。
• メールで何往復もしていた連絡が、チャットで一瞬で終わる
• 誰がどの案件を進めているか、一目でわかる
• 離れた拠点でも、まるで隣に座っているかのようなやり取り
最初に感じていた「怖さ」は、やがて「便利さ」に変わり、「安心感」「充実感」にどんどん変わっていきます。
この土台がイノベーターやアーリーアダプターの“成功事例”なんです。
ゆくゆくは社内全体の安心材料となり、さらに輻輳して、どんどん普及につながる…ということが起きるのです。
怖さを受け入れて
新しいものに挑戦するのが怖いのは、誰にとっても当たり前のことです。
でも、その怖さを理由に一歩を踏み出さなければ、今の非効率はそのまま残り続けます。
大切なのは、「小さく始めてみる」
スケジュール共有からでも構いません。小さな一歩が、不安を安心に変え、やがて大きな成果へとつながります。
新しい仕組みが普及するには「少数派が先行し、成果を示さねばなりませんそして、それを見てて「大多数が追従する」のです。
グループウェアは、挑戦した人の味方になってくれます。
怖さを感じることを否定せず、受け入れて、一歩ずつ前に進んでいきましょう。